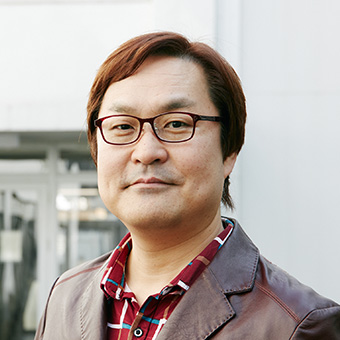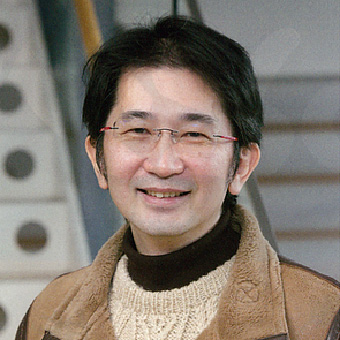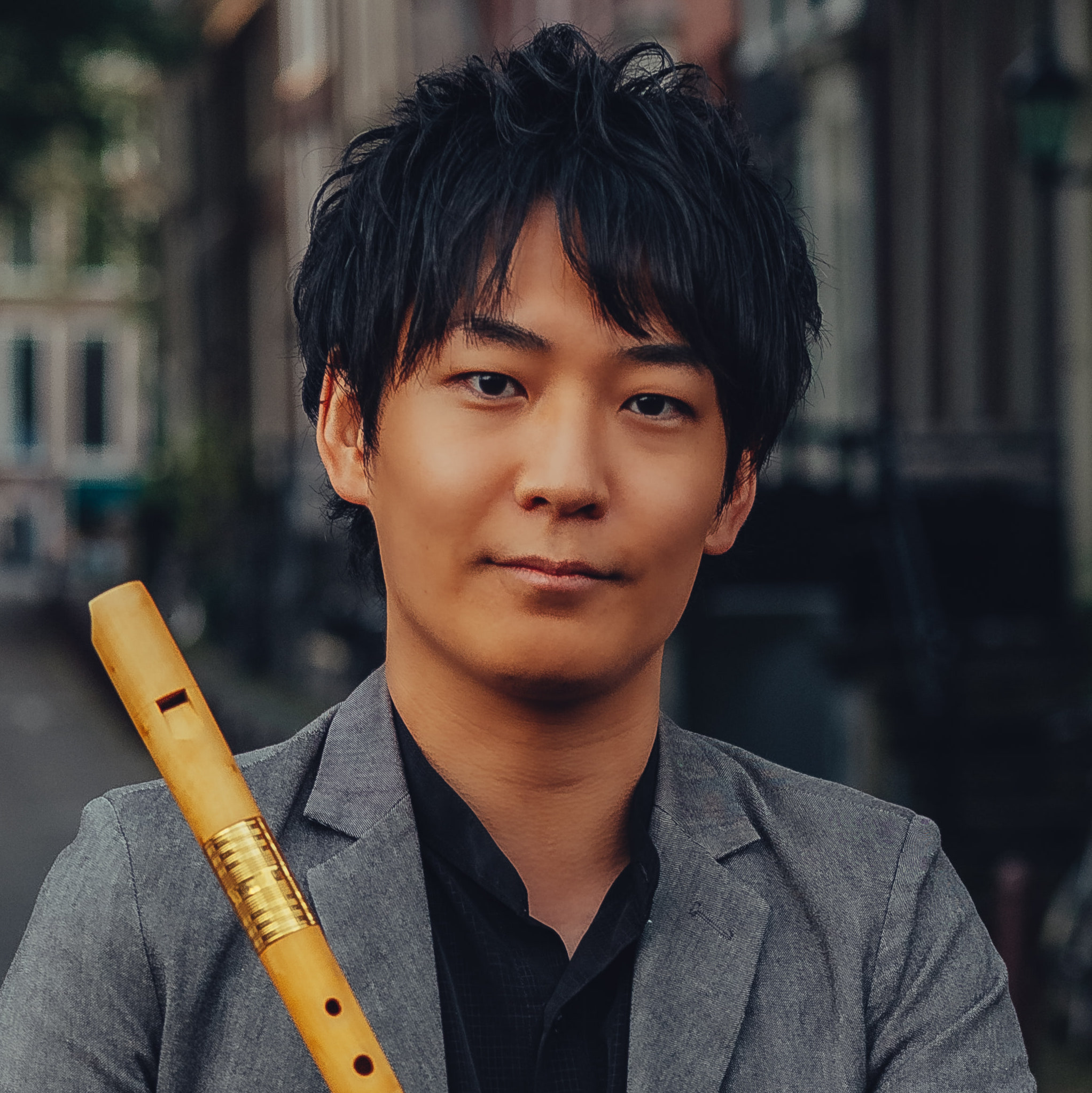アートリエゾンセンターとは
アートリエゾンセンターは、2006年9月千住キャンパス創設時に新設された音楽学部の組織です。足立区と連携しながら千住キャンパスを拠点に「音楽教育支援活動」「福祉と子育て事業」「芸術によるまちづくり事業」などの芸術文化事業を行っています。アートリエゾンセンターは、《Art=芸術、Liaison=連携、Center=組織》の名称が示すとおり芸術を通じて人や地域が連携しながら有機的に結びつくことを推進し、東京藝術大学が行う教育研究活動の成果を広く区民に提供することで、足立区の個性ある芸術環境を創造し地域社会の豊かな発展に寄与することを目指しています。